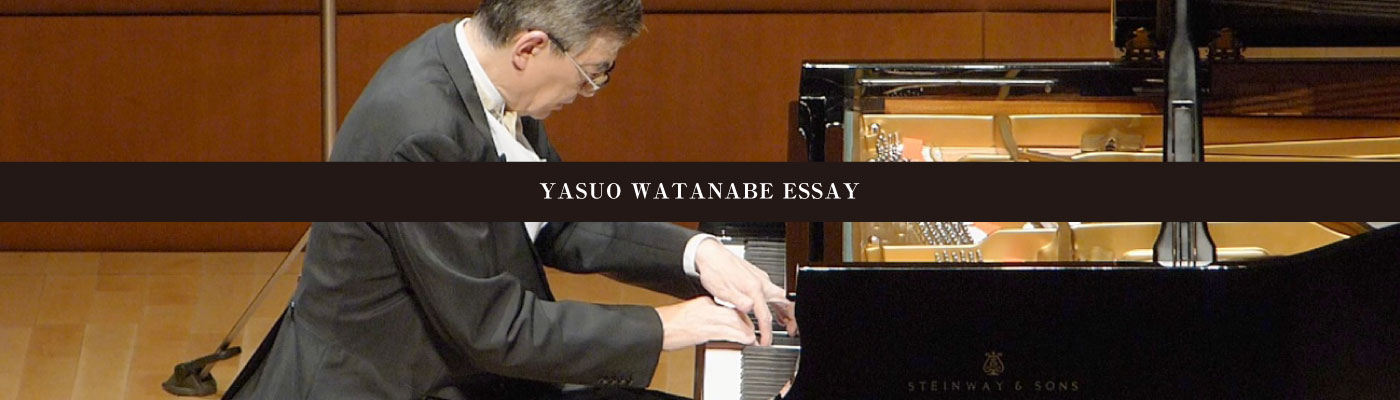|
第39回ハーモニーの家高原芸術祭2025で9月14日に演奏会をしました。

当日の演奏録画です。カーソルを合せてクリックしてみてください
当日配布した解説文です
「渡邉康雄と春日部フィルの仲間たちによる20・21世紀の音楽」 <曲目> ■ヒンデミット ヴィオラソナタ(1919)約18分 Paul Hindemith Sonate fur Bratsche und Klavier, Op.11- Nr.4 I. Fantasie, Ruhig(静かに) II. Thema mit Variationen, Rugig und einfach, wie ein Volkslied (民謡の様に静かで単純に) III. Finale (mit Variationen), Sehr lebhaft(非常に生き生きと) ■池内友次郎 序奏とアレグロ(piano solo, 1936)約9分 Tomojiro Ikenouchi Introduction et Allegro, Op.7 Tres Lent – Anime ■プロコフィエフ フルートソナタ(1943)約24分 Sergei Prokofiev Sonata for Flute and Piano, Op.94 ・・<休憩>・・ ■菊池幸夫 晩禱 ~ピアノのための~(2010)約9分 Yukio Kikuchi Vespers for piano <2010> ♩=84~92 (Tempo rubato) ■ドビュッシー フルート、ヴィオラとハープ(by piano)の為のソナタ(1915) Claude Debussy Sonate pour Flute, Alto, et Harpe 約18分 <解説> 渡邉康雄 ■ドイツのハーナウ(Hanau)に生まれたヒンデミット(1895 – 1963)は、ナチス・ドイツ時代に帝国音楽院の顧問の地位にあったが、ヒンデミットがユダヤ人演奏家たちと弦楽三重奏団を結成し名声を博したことや、アヴァンギャルドの音楽を嫌うナチスの反感を買い、ゲッペルスから「無調の騒音作家」と非難され、次第に音楽活動の場を失うようになる。代表作「画家マチス」はフルトヴェングラーの指揮により大成功を収めたがナチスがこの作品の上演を禁止したことから、フルトヴェングラーは、ヒンデミットとその作品の価値を擁護する論評を「ヒンデミット事件」とのタイトルで新聞に投稿した。この「ヴィオラソナタOp.11-4」は、ヒンデミット自身も従軍した第一次世界大戦(1914 – 1918)で、実父が戦死して敗戦となった翌年の1919年に、おそらくはフランクフルトで作曲されたと考えられる。ヴィオラが得意でカルテットなどでも演奏していたという作曲者の見事な想いが集結した名作である。三つの楽章は切れ目なく演奏される。 ■筆者が中学3年生の時に父の勧めで弟子入りした池内友次郎(いけのうち ともじろう1906 – 1991、俳人高浜虚子の次男)は、21歳であった1927年にパリ音楽院に留学した。その年はパリ・オリンピックの3年後で、リンドバーグがニューヨークからパリに初飛行を行い、「翼よ、あれが巴里の灯火だ」という映画にもなった偉業が達成された年で、両世界大戦の狭間の一瞬の良き時から大恐慌とファシズム台頭という暗黒の時代へと移行してゆく。この激動の時代に池内先生は10年という長期にわたりパリで過ごされた。同地で作曲された「序奏とアレグロ、作品7」は、先生がパリで交流のあったピアニストの原智恵子に献呈され、1934年2月23日に日比谷公会堂で原により初演された作品である。野田暉行によれば、この作品は「日本のピアノ音楽史にとっても池内先生にとっても重要な地位をしめる作品」とのこと。本日は、日本近代音楽館所蔵の自筆譜《序奏》部分と、2024年11月29日にトーキョーコンサーツラボで開催された「原智恵子110周年記念レクチャ―コンサート」で初めて明らかにされた奥村智美氏所蔵の自筆譜《アレグロ》部分とを合わせて完成した楽譜により演奏する。 (参考)池内友次郎門下生リスト 箕作秋吉 小倉朗 尹伊桑 島岡譲 貴島清彦 乾春男 別宮貞雄 宍戸睦郎 石井歓 石井眞木 松村禎三 黛敏郎 諸井誠 池野成 永冨正之 湯山昭 篠原眞 端山貢明 山本直純 間宮芳生 林光 矢代秋雄 三善晃 野田暉行 廣瀬量平 越部信義 高橋裕 池辺晋一郎 池上敏 西村朗 青島広志 (出典:ウィキペディア) ■ウクライナのドネツクで生まれたプロコフィエフ(1891 – 1953)は当時のロシアの嫌な社会情勢から脱却すべく米国に亡命し、その道中に日本に3ヶ月ほど滞在し東京と横浜でリサイタル(1918年7月6日、7日、9日)を行った。第二次世界大戦(1939 – 1945)に対する強烈な抗議心を込めたピアノの為の「戦争ソナタ」3曲(No.6(1940), No.7(1942), No.8(1944))の間の1942年に、このフルートソナタは疎開先のカザフスタンのアルマトイで書き始められ、1943年8月にロシアのペルミという町で完成させた。しかし、この曲に戦争の香りはまったくなく、独特な童話を語る様な幸せ感の溢れる作品となっている。初演したピアニストのスヴャトスラフ・リヒテルは、翌年に作曲者によりヴァイオリンソナタに改編された版(Op.94a)に「違和感を覚え自分は好きになれない」と言っていた。 ■来年2026年5月24日に開催予定である春日部フィルハーモニー管弦楽団の第7回定期演奏会に新作を書いて頂く様に依頼をしている菊池幸夫氏(1964 -、国立音楽大学教授)の、2010年に筆者が初演した晩禱(ばんとう、キリスト教における夕刻の礼拝や祈りの総称)は、その圧倒的な和音の扱いとピアノの独特な響き、それに構成的な素晴らしい魅力から再演の機会を心待ちにしていた作品である。この初演後に菊池氏が春日部高校の出身と知り、新作の依頼が実現した。敬愛する松村禎三先生の門下生である。 ■筆者が18歳で留学したボストンで知った誠に美しいドビュッシー(1862 – 1918)のフルート、ヴィオラとハープの為のソナタ(1915)は、作曲者最晩年の作で、秋のニューハンプシャー州での夕方の美しい紅葉の中で聴いた忘れ得ぬ貴重な体験があって以来、どうしても自分でその音符に直接触れたく、ハーピストの方々には誠に失礼なのを重々承知しつつ初めて鍵盤上で楽譜と対峙した。第一次世界大戦の最中に作曲されたにも関わらず、その凄惨な社会的悲劇は微塵も感じられない作品であり、その作風に調性の概念は無く、拍節と拍子感は非常にあいまいで、ソナタとの古めかしい名称とは裏腹に形式観にはまったく捕らわれていない。そして各楽器からの匂い立つようなデリケートな音色は誠に夢のごとくに美しく、武満徹などを始めとする後の作曲界の巨匠達に多大な影響を及ぼした作品である。 <春日部フィルハーモニー管弦楽団 今後の予定> 会場:正和工業にじいろホール・大ホール(春日部市民文化会館) 指揮:渡邉康雄 ◆2025年11月24日(月祝)第3回かすかべ音楽祭 ボロディン:ダッタン人の踊り サラサーテ:ツィゴイネルワイゼン ヴァイオリン:田口史織 ガーシュイン:ラプソディーインブルー 弾き振り:渡邉康雄 ホルスト:木星 菅野よう子:花は咲く ◆2026年5月24日(日)第7回定期演奏会 モーツァルト:交響曲第41番「ジュピター」 菊池幸夫:<新作初演> ムソルグスキー・ラヴェル:組曲「展覧会の絵 」 |